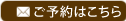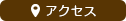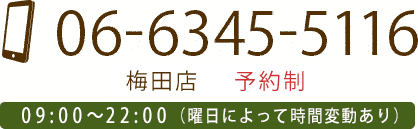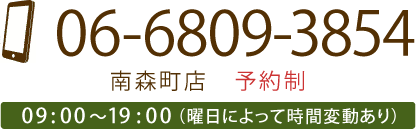ヒトの腸は、植物の根を調べるとさらに微生物の重要性がわかる
当サロンで発刊している毎月のニュースレターでも紹介したこの本、興味を持った人は相当マニアックな人だけかもしれません。健康について考えている人、医学、医療に関係のある人、体調の悪さをなんとかしたい人にオススメです。
それだけではなく、植物を愛する人、観葉植物が好きな人、家庭菜園をしている人にもオススメな本。身体のことと植物への理解が深まり、同じ生物としての仲間だという意識が芽生え、植物がさらに好きになります。
腸の機能と構造は、植物の根っこと似ている
腸は身体の内側にあるように思えますが、実際のところは腸の中は「身体の外」です。腸から吸収されて初めて「身体の内」に入ります。
腸内細菌は「身体の外」にいて、栄養を吸収した後は「身体の内」となります。
この構造を前提として、植物の根っこについての話とヒトの腸についての話が広がる本です。
多くの微生物はヒトを助けてくれる
微生物は自己の遺伝子を簡単に調整できるのだそう。環境に適応するために自分の遺伝子を変更していくんですね。環境というのは、ヒトで言えば腸内細菌叢。宿主となるヒトが健康な状態を保ってもらうために、微生物は柔軟に遺伝子を変えて適応し、ヒトがいい状態になるようにと共生の道を歩みます。こうやって聞くと健気なものですね。なかには病気をもたらす微生物もいますが、多くの微生物はヒトにいい影響を出してくれるのだそう。
腸内細菌といえば悪玉菌・善玉菌・日和見菌という分け方ができますが、微生物という大きなくくりで考えれば、悪玉菌にも役割があり日和見菌にも意味があるということがわかります。
現代人の生活習慣病は腸の微生物の変化のせい?
筆者は、「感染症に変わって慢性疾患が増えた」のは微生物の集合体の影響だと書いてます。食の変化だけではなく、野菜を育てる土も化学肥料へと変わった影響もあるかもしれませんね。
僕の個人的な意見となりますが、1日3食の習慣が根付いたことが原因なんじゃないかと考えています。
日本でも欧米でも、100年前までは1日1食?2食が主流でしたが、日本でも欧米でもほぼ同時に3食の文化が広まりました。
エジソンがトースターを発明し、「トースターを売るにはどうしたらいいだろうか」と考え「そうだ、朝もご飯を食べるよう宣伝しよう」というマーケティングの成果かもしれないし、戦後の日本にドイツの栄養学が入ってきて政府が朝ごはんを食べるよう言ったからかもしれません。
朝ごはんが広まった理由は諸説ありますが、1日3食によって、生活習慣病が起きているような気がしています。
それはともかく、ハワードという人物が1930年代に微生物の影響じゃないかと考えていろいろ調べたそうです。
堆肥で育った野菜を食べると健康になった事例
1930年代、サー・アルバート・ハワードという人物が「微生物が土壌肥沃土だけでなくヒトの健康も促進する」という考えを持っていました。しかし、そのメカニズムを説明できずにいました。
ちょうど、ロンドン近郊にある大規模な男子校の経験によってはっきりと堆肥で育てた野菜を食べた方が健康になるとわかったそう。
「学校の先生は学生に食べさせるために野菜をたくさん栽培していた。学校が野菜の栽培方法を化学肥料からインドール式の堆肥へと切り替えてからなにが起きたか、ハワードは追跡した。すぐに学校に蔓延していた風邪、麻疹、猩紅熱が、通学生がたまに持ち込むまで著しく減った。ハワードは、肥沃な土壌で育った新鮮な食べ物はヒトの健康を促進すると結論した。(P286)」
と書いています。
1930年代から化学肥料による影響があったんですね…。
この本を読んでから、土を育てています
腸内細菌のためには発行食品や漬物など乳酸菌や善玉菌が多いものを食べたりはしてましたが、土を良い菌で育ててみようと考えました。その土で植物を育てるとどうなるか?それが楽しみで今は土を育ててます。
普通の土に乳酸菌飲料と月桃茶の茶葉を混ぜています。
おそらく良い菌が育ちやすい土ができたので、当サロンにある観葉植物の「がじゅまる」に土を少し与えて違いを見ています。やはり、良い土を与えた方が葉っぱが多くなってる気がしますが、季節的なものもあるかもしれませんね。春が近づいているので葉が多くなっているのかも?
まだまだ様子見の段階です。